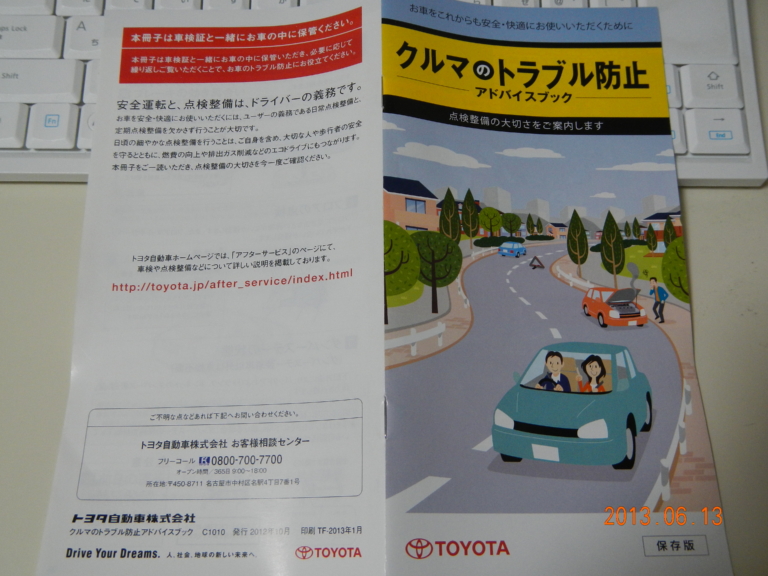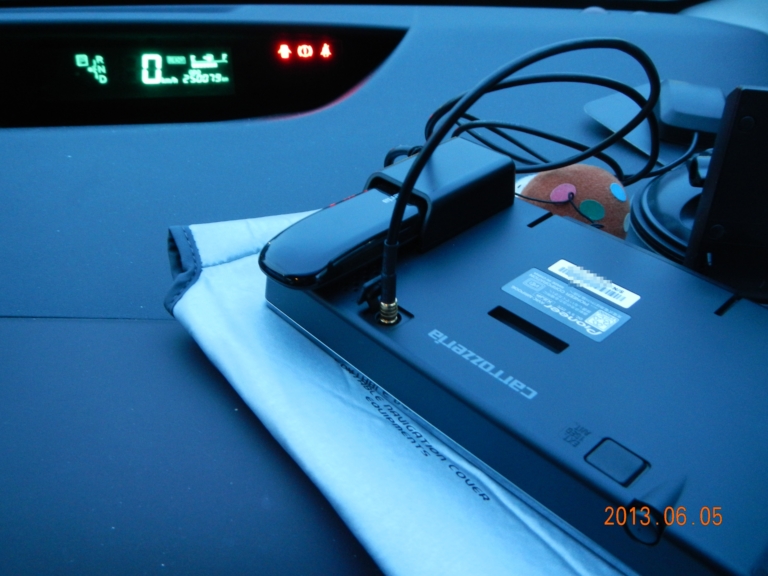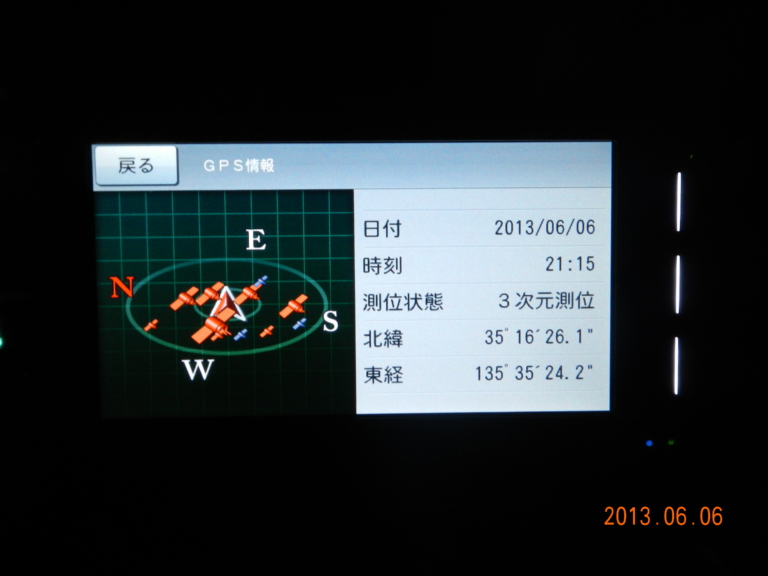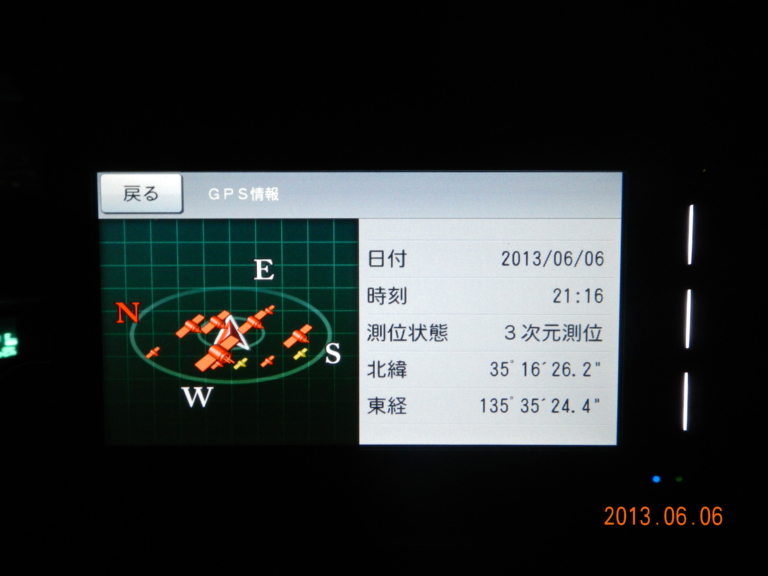ひさびさの雑誌レビュー。特集が”農協支配の終焉”ということで『のうりん』シリーズのような強烈な話かと期待して読みました。パロディまみれ品のかけらも無いライトノベルの後追い特集ということで。
…。内容が無い。農協に絞るなり品目を米や野菜などどれかに絞るということも無くテーマがバラバラでこんな問題、あんな問題があります。こんな組織もありますという紹介記事だらけ。最も参考になるのがJA全中会長さんのインタビューだったり。質問が利潤追求の方向に偏っているような気もしますけど、現組織を維持するという責任を負った彼の立場がよく分かる内容です。まとめ方はポジショントークそのものという記事になっているような。
『のうりん6』を読んでいたら281ページの
日本の農業人口は二十六万人(注)。平均年齢は六十六歳。
普通の企業なら定年退職している年齢だ。
二十六万人(注)のおじいちゃんおばあちゃんが、先祖伝来の田んぼや畑だけは残そうと、都会に出て行った子供の家族に米や野菜を届けてあげようと、ほとんど使命感だけで農業を続けている。
(注)統計上正しくは平成23年は 260万人農林水産基本データ集(http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/)より、もう片方の平均年令は正しく平成23年は 65.9歳、同データ集より。
こんなフィクション作品の表現の方が手厳しいかと思います。TPPやアマゾンの参入といった外的要因も問題かもしれませんが、それ以前に現状維持が自滅への道と繋がっていないかという検証はどこへ?
私は儲かる農業への転換をして利益が上がれば農家が満足して存続できるというわけでは無いと思うのですけど、この点については農協サイドの主張に繋がる(と判断された)ためか触れていません。
残念ながら、農業だけでは無く家電など他の産業も同じような衰退を見せている現状でどこか他人事な特集記事でした。大手出版社には関係ない?出版業界は成長産業なのでしょうか。利潤追求でこんな特集を組んだのだろうか?疑問だけが残る号でした。