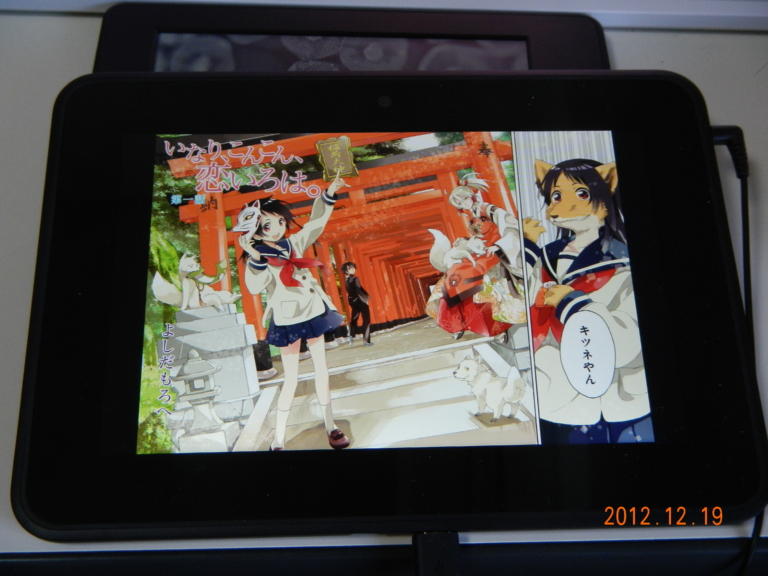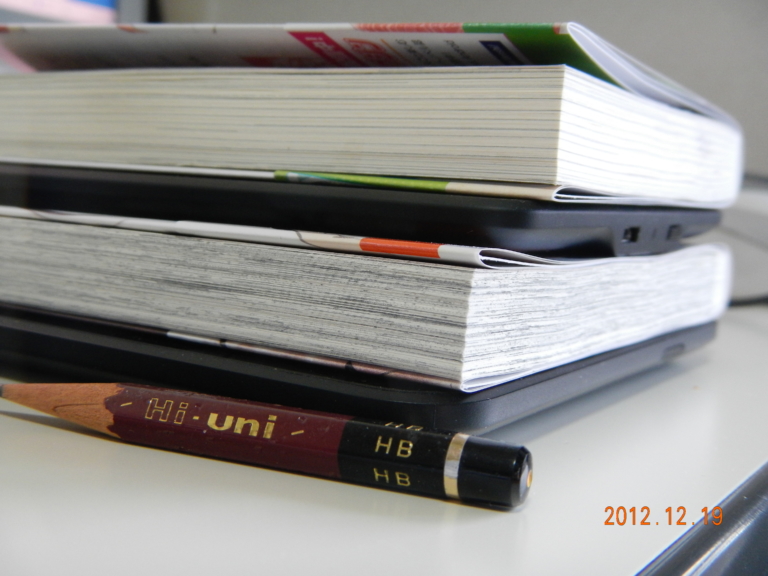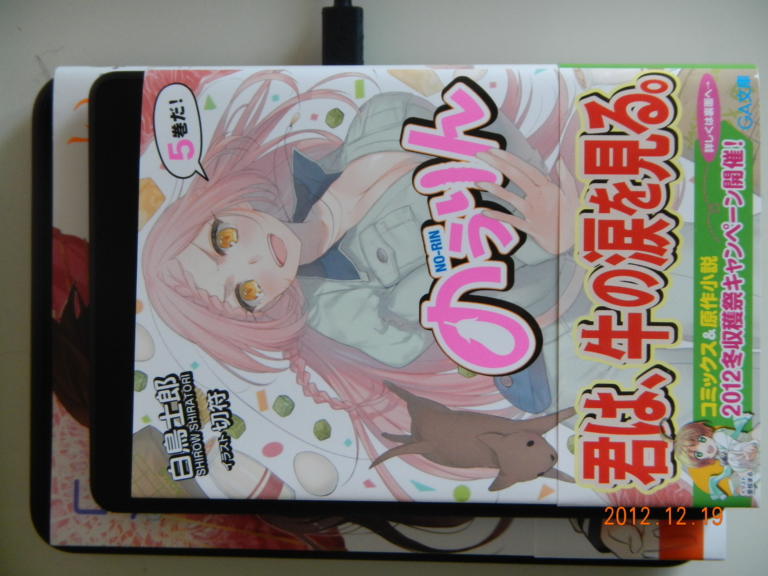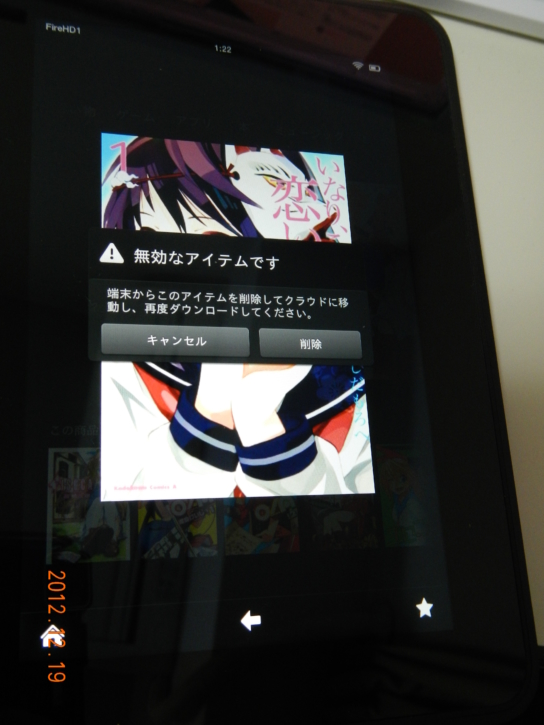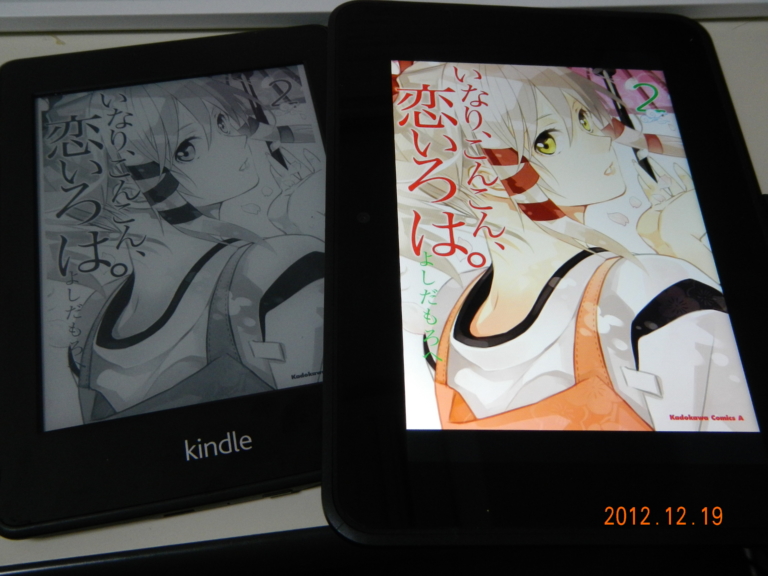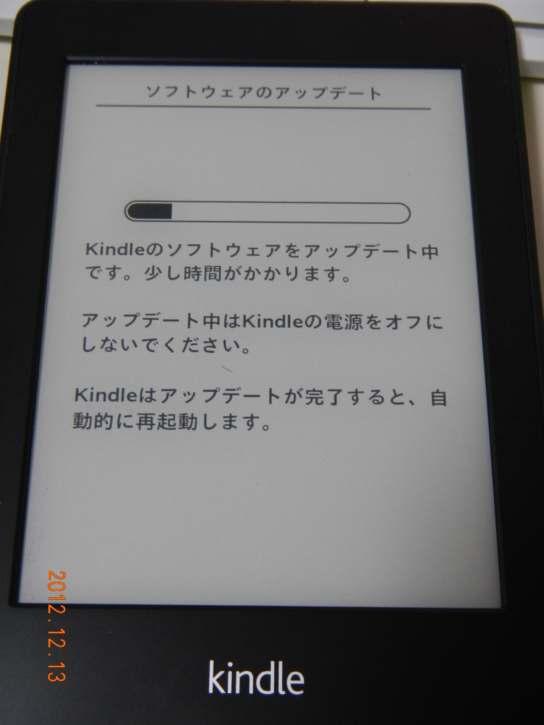別件で電話したところ届いているということで、急遽京都トヨペット七条本店へ行きNV-SP200DTをリプレースする新ポータブルナビを受け取りました。直接の決め手は本体というよりは通信アダプタのキャリアが2年前に検討したモデルのSBMからdocomoへ変わり、値段が大幅に安くなった点が大きいです。モジュールについては別に注文しているので届いてから書きます。
 仮設でAVIC-MRP006, NV-SP200DTを並べて試走
仮設でAVIC-MRP006, NV-SP200DTを並べて試走
液晶モニタも6.1VワイドとNV-SP200DTより大きくなおかつ解像度も高いためかなり見やすくなっています。NV-SP200DTと比べて良い点をざっと並べてみると、以下の通り。
動作が極めて速い
リルートが特に速い
表示の更新が速すぎてちらつくように感じる場合もある
液晶が見やすい
地図データは同じでも見せ方に一工夫がある
文字拡大モードで読みやすくなる
表示される地図の範囲が広く周囲の道が把握しやすい
2時間連続運転での警告アナウンス(高速での休憩目安)
案内開始時に目的地までの距離と所要時間をアナウンス
(到着時に実際に掛かった時間もアナウンス)
県境アナウンス(なぜかゴリラプラスには無かった)
目的地検索の仕方がゴリラプラスと微妙に違う
パイオニアのナビを使ってきた人ならば違和感ないかも
毎月地図更新(年2回全更新、2015年10月まで3年分本体料金込み!)
通信モジュールがやたら安い
回線契約不要
スマートループ渋滞情報対応
付属のシガーライター電源ケーブルが12V/24V両対応
ただし、何もかも良くなるかというとそうでもなく、
コールドスタート時に位置特定が遅い(ジャイロはゴリラの方がいいかも)
トンネル内で減速すると自車位置が出口で止まる(ジャイロのみでの精度が低い?)
交差点名を読み上げない(右言われてもどこを右かわからん)
案内標識表示機能無し(雪で見にくい時に重宝しました)
バックライト輝度の自動調整が無い(最低でも明るすぎ、トンネルなど一時的に暗くなると困る)
到着時刻の予測に平均車速が使えず固定(郊外は乖離する傾向にあります)
スピーカーの性能が微妙(通信モジュールの取付位置がスピーカーの目の前です)
週間天気予報が見られない(目的地の天気も知りたいところです)
地図上でアイコンをタップして施設情報が出ない(店名や営業時間などが分からない)
高速道走行時にPA/SAだけの表示ができない(ゴリラプラスで使えていた機能)
アンテナ表示でFOMAの電波状況が簡単に見られた(圏外場所の把握が簡単だった)
などぱっと見てゴリラプラスの方が良かった点もあります。メーカーによらず通信ポータブルナビにAV機能など全く不必要なのでばっさり削ってコストダウンしたモデルが欲しいです。AVIC-MRP006は3つしかないハードボタンの内一つが死んでるのが無駄。ワンセグも要らない。あえて付けるならばETC/DSRC連動やAM 1620/1629kHzの受信機能では?
リアカメラにも一応対応していますがシフトレバーと連動せず使えません。こんなところで差別化するのもばかばかしい気がします。
 交換後新品(2012年第40週製造)
交換後新品(2012年第40週製造) 交換前(2011年第45週製造+17161km走行)
交換前(2011年第45週製造+17161km走行) 外観はピカピカな点以外変更無し。
外観はピカピカな点以外変更無し。